郷土(ふるさと)の森づくり
製鉄所に鎮守の森を再現し生物多様性も育む
当社は、自然と人間の共生を目指して、故 宮脇昭氏(横浜国立大学名誉教授)のご指導のもと、製鉄所の「郷土の森づくり」を推進してきました。これは、近くの歴史ある神社の森(鎮守の森)でその土地本来の自然植生を調べ、地域の方々と社員が苗木を一つひとつ丁寧に植えていくものです。日本の企業で初めてのエコロジー(生態学的)手法に基づく森づくりとなり、郷土の森は地域の景観に溶け込んでいます。今では、約850ヘクタール(東京ドーム約180個分)にも及ぶ森に育っています。
全国の製鉄所の森には、多様な生物たちの姿も見られます。土地本来の木々に、土地本来の野生生物たちが帰ってくるのです。このように「郷土の森づくり」は、CO2吸収源としての役割とともに、生物多様性の保全にも大きく貢献しています。



各事業所の野生生物たち
製鉄所内の森は生物多様性の保全にも役立ちます。
ヒヨドリやワシなどの野鳥たちが集い、キタキツネやシカなど多様な野生の生物たちの姿も見られます。
各事業所の野生生物たち
| 室蘭 | エゾシカ、キタキツネ、エゾリス、ワシ、ノスリ、カササギ |
|---|---|
| 釜石 | ツキノワグマ、カモシカ、シカ、ノウサギ、ウミネコ |
| 直江津 | ウグイ、コイ |
| 鹿島 | キジ、モズ、カモ |
| 君津 | ヒヨドリ、キジ、コアジサシ、ツバメ、シラサギ |
| 名古屋 | タヌキ、キジ、ヒヨドリ、モズ、ツバメ、シジュウカラ |
| 尼崎 | サギ、ヒヨドリ、キントカゲ、メダカ、シオカラトンボ |
| 大阪 | イタチ、ムクドリ、ヒヨドリ |
| 堺 | カモ |
| 和歌山 | タヌキ、テン、ヒヨドリ、ヤマカガシ |
| 広畑 | ノスリ、モズ、キジバト、ヒヨドリ、ムクドリ、ホオジロ |
| 光 | ウミネコ、セグロカモメ等51種類の鳥 |
| 八幡 | イタチ、キジ、アオサギ、ウミウ |
| 小倉 | カモメ、セグロセキレイ、アオスジアゲハ |
| 大分 | オオハクチョウ、カワセミ、メダカ、カゲロウ、ホタル |

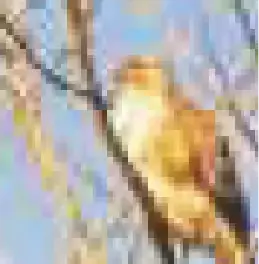
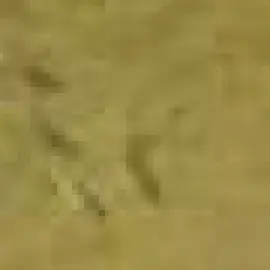





製鉄所の地域に根ざした森づくり
「企業の森」に参加

当社は、和歌山県の森林環境保全事業「企業の森」に参加しています。この事業は、森林整備を行いながら和歌山県の自然環境の保全を目指すもので、企業が植栽などのボランティアを行います。田辺市中辺路町の民有林2.5ヘクタールを借り、「日本製鉄和歌山の森」と名付けられたこの事業において、2005年から10年間で広葉樹を中心に5,000本の植樹を行いました。現在は、別区画1.76ヘクタールを対象に活動しており、日常の管理は中辺路町森林組合に委託し、植樹と下草刈りなどに社員が参加しています。
また、和歌山県内の林道の簡易舗装にあたり、関西製鉄所 和歌山地区の副産物である鉄鋼スラグからつくられたカタマ®SPが使われています。


新入社員による植樹

千葉県にある東日本製鉄所 君津地区では、環境教育の一環として、新入社員による植樹を毎年行っており、シイ・カシ・タブなどの常緑広葉樹を植えています。
都市型製鉄所における工場緑化
大阪府にある関西製鉄所 製鋼所地区では、ヒートアイランド現象の緩和や、建物温度上昇抑制による省エネルギーに効果がある「壁面緑化」や「屋上緑化」を行っています。


地域の環境保全活動への参加

北海道にある室蘭製鉄所では、室蘭市主催の「市民植樹祭」に、社員が毎年参加し、地域の子どもたちとともに、植樹をしています。また、市内にある400mもの大型花壇の下草刈りや苗木植えなどを社員が実施しています。
IGES国際生態学センター
センター長 鈴木 伸一
1971年に植栽が始められた大分地区の「鎮守の森」(以下、郷土の森)は、1920年植栽の明治神宮の森と同じ人工の森である。しかし、単なる人工の森ではない。故 宮脇昭先生が植生生態学の研究成果から考案し、綿密な計画、管理のもとに創生され、現在では世界的に評価されている「宮脇方式」による常緑広葉樹の環境保全林である。
植栽後50余年で既に樹高20mに達し、明治神宮を彷彿させる森に生長した大分地区の郷土の森は、工場緑化の枠を超え、修景的にも優れた地域の植生景観を構成し、防災、防塵など総合的に環境保全効果の高い樹林地帯を形成している。工場緑化といえば、支柱のある成木の単植が主流であった1970年代にあって、生態学的手法を取り入れた日本製鉄の環境保全に対する先見性は、高く評価される。
実は、現在の郷土の森も植栽を行う前は海岸埋立地の裸地であった。そこに樹林形成を可能にしたのは、現地調査による郷土の自然林:潜在自然植生の判定とその構成樹種の育苗、土壌改良、マウンド造成などの生態学的植栽手法である。しかも大分地区の郷土の森の樹林は植栽後50年を経てもまだ発展途上にあり、今後も生長、発達を続ける生きた環境保全装置として、温暖化、生物多様性など地球環境問題対策への高い効果と貢献が期待される、貴重な自然資本である。

鈴木 伸一 氏
植生学者。IGES国際生態学センターセンター長。博士(学術)
1958年群馬県生まれ。明治大学農学部卒業後、横浜国立大学環境科学研究センター植生学研究室にて、宮脇昭先生に師事、薫陶を受ける。群馬県立高等学校生物教諭、IGES国際生態学センター研究員、東京農業大学短期大学部教授・同大地域環境科学部教授を経て2024年7月より現職。環境省植生図凡例検討委員、経産省環境審査会顧問。群馬県尾瀬保護専門委員。公益財団法人鎮守の森のプロジェクト技術部会長。
共著に『日本植生誌第3~10巻』(至文堂、1983~1989)、『植生景観とその管理』(東京農大出版会、2014年)、『環境を守る森を調べる』(海青社、2018年)など。