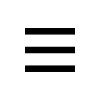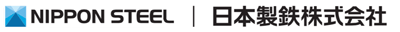チタンと鉄の違いとは?軽量性を活かした自動車部品への活用事例
 チタン基礎
チタン基礎
チタンと鉄は金属を代表する種類です。実際に、私達の生活の中にチタンと鉄は溢れており、日頃から目にする機会も多いでしょう。
また、チタンはさまざまなメリットがあり、アウトドア用品だけでなく、安全を担保しなければならない自動車部品などにも使われています。そのため、さまざまな用途で使用することが可能です。
しかし、チタンと鉄の違いについて明確に答えられない方も多いのではないでしょうか。違いを知ることで、チタンの特性やメリットをより細かく理解することができます。
今回は、チタンと鉄を意匠性やカラーバリエーション、素材寿命の観点から比較し解説します。また、チタンの軽量性を活かした自動車部品への活用事例についてもご紹介しますので、興味のある方は、ぜひ参考してください。
チタンの特性
チタンの特性は、大まかにわけて3つあります。鉄と比較しながら特性について詳しく解説しますので、ぜひチェックしてください。
チタンは鉄やステンレスの60%程度の軽さ
1つ目の特性は、軽量な点です。下記の表をご覧ください。
| 金属の種類 | 比重 | チタンとの比較 |
|---|---|---|
| チタン | 約4.51 | 1倍 |
| 鉄 | 約7.8 | 約1.74倍 |
| ステンレス | 約7.9 | 約1.75倍 |
チタンの比重は、約4.51であるのに対して鉄は約7.8です。また、ステンレスは約7.9になります。これらの素材に対して、チタンは60%程度の軽さになるため、ほかの金属と比較して軽量であることが証明できるでしょう。
チタンを素材として使用すれば、モノの軽量化を図ることができます。そのため、軽さを追求する際に採用される金属のひとつです。
チタンの比強度は鉄の約2倍
2つ目の特性は、鉄と比べて強度が約2倍あることです。下記の表では、それぞれの素材を引張強度で比較しました。
| 金属の種類 | チタン合金 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ステンレス | アルミニウム |
|---|---|---|---|---|
| 引張強度(N/mm2) | 約999 | 約490以上 | 約74.4 | 約75.7 |
強度を見ると鉄の約2倍の強度を持つことがわかります。ステンレスやアルミニウムなど、ほかの素材と比較しても強度は負けません。
このような特性のため、大きな衝撃を受けても破損しづらいです。そのため、ロケットや航空機の部品など、耐久性が求められるところで頻繁に使用されています。
チタンは鉄の2倍たわみやすい
3つ目は、たわみやすいという性質です。ほかの素材に比べて高強度を誇りながら素材には柔軟性があり、鉄よりも曲がりやすくなります。つまり、しなりやすいのです。
鉄やステンレスと比較すると2倍たわみやすいといわれています。そのため、金属の中でもバネ特性を持つ素材です。
鉄と比較したチタンのメリット
鉄と比較したチタンのメリットは下記の3点です。
- 耐食性
- 意匠性
- 軽量性
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
チタンは耐食性が高く錆びにくい
1つ目のメリットは、耐食性に優れていることです。鉄は水などに触れると表面が溶解します。そして、イオン化減少が始まるのです。空気中に酸素と溶け込み、水酸化イオンになり、その後に酸化鉄を発生させます。これにより、錆が引き起こるのです。
一方、チタンは酸化皮膜という不動態皮膜を形成します。簡単にいえば、本体を守るための薄い膜です。これにより、水などに触れても錆びにくく、耐食性が高いといわれています。
また、水はもちろんのこと、海水にも強い素材です。そのため、塩水の付着が心配される部品などにも使用されることが多くなっています。
外観の意匠性を高めるカラーバリエーション
2つ目のメリットは、カラーバリエーションが豊富であるという点です。チタンは約100種類以上発色させることができます。それは塗装によるものではなく、光によって実現される色です。
チタンの本体は酸化皮膜で覆われています。酸化皮膜は無色透明なため、光の一部は酸化皮膜を通り屈折して反射します。一方、それを通らず反射する光もあるのです。これらの光が混ざり合って目に届くことで、私達は発色していると認識します。
実際に発色させるためには、下記のような表面処理をする必要があります。
- ロールダル仕上げ
- 洗仕上げ
- エンボス仕上げ
- ヘアライン仕上げ
- バイブレイション研磨仕上げ
- 鏡面仕上げ
これにより、豊富なカラーバリエーションを実現することができます。発色によって多彩なカラーを実現できるため、塗装をする必要がありません。塗料を必要とせず、発色による美しい色を楽しめることもチタンの大きな魅力であるといえるでしょう。
軽量かつたわみやすい特性で自動車部品を軽量化できる
3つ目のメリットは、自動車部品の軽量化を実現できることです。チタンは、鉄やステンレスと比較して約60%軽量な素材になります。また、バネ特性を持ち鉄の2倍たわみやすい金属です。そのため、自動車部品の軽量化に活用されています。
自動車部品軽量化の取り組みは、1980年代から行われるようになりました。その理由は、車体重量の増加が自動車メーカーの課題だったからです。その頃から安全性を考慮して安全装置の搭載が進められていました。当然、車体に組み込むため、その分重量が増加してしまいます。また、排気ガス規制の厳格化が進められた時代でもありました。それも軽量化を後押ししたのです。
軽量化はレース車を中心に行われました。その後、低コスト化などの開発が進み、私達が使用する車にもチタン素材の部品が数多く使われるようになったのです。
このように、チタンは自動車の軽量化に一役買っている金属です。そのため、需要が高く、私達の暮らしに欠かすことができません。
チタンの軽量性と意匠性を活かした自動車部品のチタン化
先程、自動車部品の軽量化について触れましたが、実際にどのような自動車部品にチタンが使われているのでしょうか。チタンが使われている自動車部品について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
駆動部品や燃料タンクの軽量化
チタンは駆動部品や燃料タンクに使われています。駆動部品とはエンジンバルブなどです。駆動系部品を軽量化することで、周辺部品の負担を軽減することができます。また、レスポンス性の向上なども期待できるため、大きなメリットです。チタン合金は、引張強度が強いため、エンジンバルブ等の駆動部品で使用することが可能となりました。
燃料タンクの軽量化にもチタンが採用されています。特に、二輪自動車は、燃料タンクが高い位置にあるため、重量が高いと操作性が損なわれます。軽量化を図ることで、低重心化を実現できるため、操作性の向上を果たすことができたのです。
このように、自動車部品の中でも重要なパーツにチタンは使用されています。
干渉色で表現するマフラーやボルトのデザイン性
チタンの発色を活かし、デザイン性を向上させるため、自動車部品で採用されるケースもあります。例えば、マフラーやボトルなどです。
チタンは表面を覆う酸化皮膜の厚みを制御することで、100種類以上の干渉色を表現することができます。また、干渉色と素地を組み合わせ、質感と色調を調整することで意匠性を高めることも可能です。このような理由から二輪自動車のマフラーやボルトなどにチタンが採用されています。
まとめ
今回は、チタンと鉄の違いや自動車部品への活用例についてご紹介しました。チタンは、その特性からさまざまな分野で使用されている部品です。自動車業界もそのひとつであり、燃料タンクやエンジンバルブなどの軽量化を実現しています。このように、チタンは意匠性や軽量性に優れており、私達の暮らしに欠かすことができない素材です。